「人間は泣きながらこの世に生まれてくる。
阿呆ばかりの世に生まれたことを悲しんでな」。
これはw・シェイクスピアの言葉であるらしい。
いやはや、なんとも豪胆な。
シェイクスピアと言えば、ご存じ世界一有名な劇作家。
ロミオとジュリエットやハムレット、リア王なんて誰もが知っている名作である。
私は劇場で見たことはないが、
映画大全集は持ってるんだなぁ(笑)
作品の全てがドキッとするくらい人間の内面を表現しているので、
個人的には心理学者や哲学者に近い気がする。
全ての人間が持つ原罪である猜疑や嫉妬、
マクベスはこれを鮮明に描き出した。
喜劇と史劇と悲劇・・・。
今回はそんなシェイクスピアにまつわる小話。
☞ ☞ ☞
シェイクスピアは活字を使わなかったらしい。
台本は個人のパートだけ与えられ、全体の物語を読むことができかった。
当然、観客も作品を見る事ができない。
つまりは耳でしかその舞台は体験できないものだったのだ。
実際の舞台と俳優のセリフを覚えながら各自、
一連の物語を再構成するしか、方法はなかった。
よって観客を始め、俳優たちそれぞれも、
各々が自由にその世界を感じたのである。
よってシェイクスピアの舞台そのものは
一義ではなく、多様な物語なのだ。
何と不親切な・・と思うだろうか?
私はそうは思わない、むしろ逆にこれこそが醍醐味である。
我々がその一部始終を目にできるような俯瞰的な視点とは
逆を言えばそのリアルな「場」から切り離された傍観者でもある。
そして客観的な場に居座れない代わりに、
我々は常に参加し、受け入れ、相互に影響を与えあうことができる。
内側から眺める視点、これがunreveの「場の創造」なのだ。
文字(テキスト)が存在すれば途端に内部から外部となる。
まるで台本を読む傍観者のように。
つまり全員が参加するには「文字」が邪魔なのだ。
岡目八目は立ち位置として重要だと書いたが、
その視点を自由に変える事ができるのが前提としてある。
☞ ☞ ☞
シェイクスピアの演劇は没後、その「曖昧さ」から
数学者からなる王立協会によって批判された。
それは数学者やプロテスタント(カルヴァン派)が求める
「万人共有」の対立概念だったからだ。
17世紀は「多様から一義へ」変わって行った時代ともいえる。
シェイクスピアの没後、世界中の人々が作品を共有した。
印刷技術とは、世界で初めての大量生産した「知の共有」である。
つまり今ある活字本とは、均質にして反復可能であり、
編集によって多くの人々が共通する意味を持てる、という
「再現性を売る商品」なのだ。
否、持てると勘違いさせてしまう商品なのである。
☞ ☞ ☞
フランシス・ベーコンは言語が個人の偏見(イドラ)によって
作られているとし、
デカルトは観念を正確に伝えうる言語以外の記号を考えた、
言語が記号である以上、解釈は一つではないのだ。
フランチャイズのマニュアルも当然「イドラ」である。
その台本を俯瞰しても捉える「フィルタ」が違うのは当然だ。
我々は自己完結、つまり「勝手に納得(解釈)」してしまう。
(解読と解釈の違いは前回書いた)
シェイクスピアはそれを危惧して、
あえて台本を書かなかったのかもしれない。
多様な捉え方そのものに価値を置いた気がしてならない。
つまり受け手が多様である以上、
一つの台本を作ったとしても、その解釈は多様のままなのだ。
unreveは「参加型マニュアル」を推進している。
それは本部と加盟店によるフラットな編集作業だ。
イノベーションが求められる時代において、
既存の閉鎖的になりつつある専門性や、俯瞰的マネジメントは台本である。
台本に当てはめ、再現し、大量に作る。
それはもう通用しない。
現在、時代を先読みする地図はない。
管理する設計書もない。
今はコンパスだけが頼りなのだ。
それは関係性の中から生まれる気がしてならない。
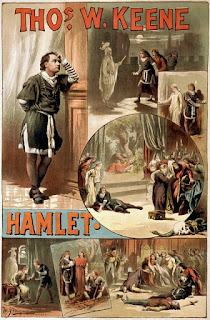
0 件のコメント:
コメントを投稿